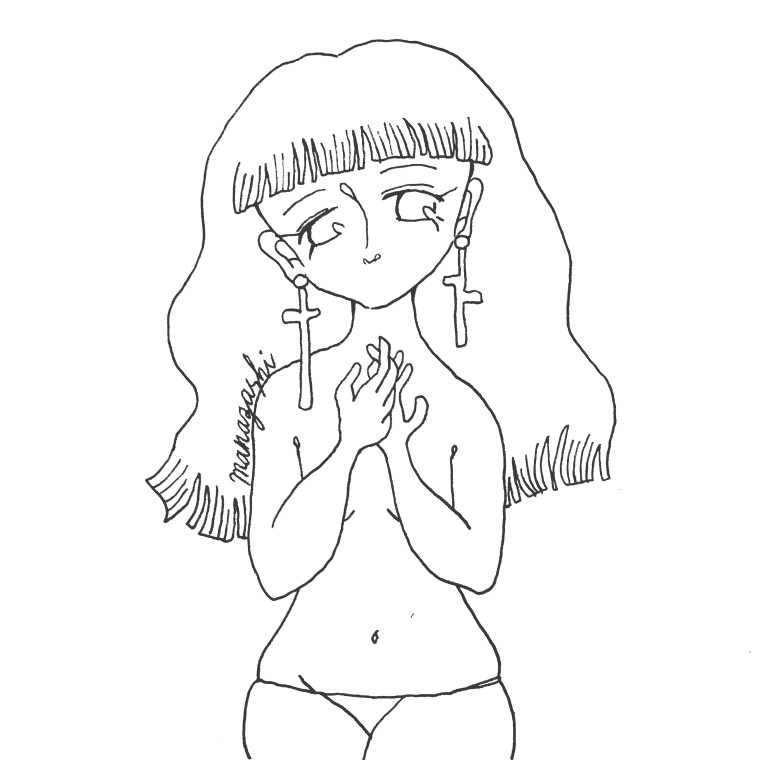連載第1回目から読む
→現代を生きる乙女の祈りと、淡水パールのいびつなクロス
硝子にメタル、宝石、ウッド、動物の骨や角。
装身具を構成する素材というのは実に様々な範囲に及んで、そのひとつぶひとつぶ違った個性豊かな質感や、光の放ち方をどれも大切にしていますし、一個の作品のなかでつつましくその役割を果たす全てのビーズたちがとても愛おしく思えます。
そんな山の様な素材の中でわたしがある意味特別な愛を寄せているのが、プラスチックです。アクリル、という表記の方が最近は多い気がしますが、「プラスチック」という音の響きの方が、わたしが抱くこの素材への愛の内容にどこか近しい感じがあります。
おそらく多くの女の子がこの懐かしい記憶を共有していることでしょう。デパートのおもちゃ売り場で、または町の駄菓子屋さんで、お祭りで・・・プラスチックで出来た、ニセモノの宝石のジュエリーが放つ煌めきに憧れ、それをねだった記憶を。
あの魔力の正体は何だったのでしょう?大人になったいま改めてそれらを眺めてみると、何とも品の無いチカチカ空しい光ばかりをこの目は捉えてしまいますし、みなどうしようもなく安っぽいのです。かつての少女たちの眼をときめかせた光は、「たわいもないもの」として段々と遠ざけられてゆき、そしてそれはとても自然なことであるように思えます。
けれどもわたしにはその「たわいもないもの」が、どうしても見捨てられないのです。それどころかこの煌めきには、ある特殊な美学に似たものが存在するように思えてなりません。そしてそれは何にも、たとえホンモノと呼ばれるものにも、決して侵されない気がするのです。
ところで現代に生きる極めて平凡な女の子(であった)の端くれとして、時々ふと考えることがあります。リアルの世界に、液晶上に、様々な理想像が暴力的にはびこる時代、知らず知らずの間に私たちはその像を崇拝し、勝手に劣等感に苛まれてる。どんなに頑張っても、「特別」とか”special”と尊ばれるものに追いつけないこの宿命を、意識せずとも痛感してしまっている。その特別なものって果たして何なのかは実はよくわかっていない、しかしこの自分の喘ぎはきっとどこかありきたりで、ひょっとしたら誰か何かの真似ごとに過ぎなくて、ずば抜けて優れたものではないことも、ちゃんと何処かで理解をしている。
わたしにはプラスチックの煌めきが、そんな女の子たちのたましいに寄り添い、共鳴しながらそれを輝かせるものとして、ぴったりなもののように思えました。
このプラスチックビーズのシャンデリアーイヤリングは、現代に生きるそんな女の子たちのうつくしさを想って制作しました。わたしはそういう生き方にひとつの美を見つけます。たとえ誰がそれをどう呼ぼうと、誰が彼女たちひとりひとりの痛みや喘ぎを殺す権利があるでしょうか。それは何からも侵されない事実であり真実であるはずで、それが放つ火花は確かな生の煌めきであるはずで。
まばゆい程に光って欲しい、何よりも輝いて欲しい。ありきたりで凡庸な存在の、ありきたりで凡庸な感情が、高価な宝石よりもずっと尊い最強のタカラモノになる瞬間を逃したくなくって、わたしは自身の苦しみも愛して生きてきた気がするし、何処かの誰かが自身のそれを否定して消えていってしまわないで欲しいって願っています。
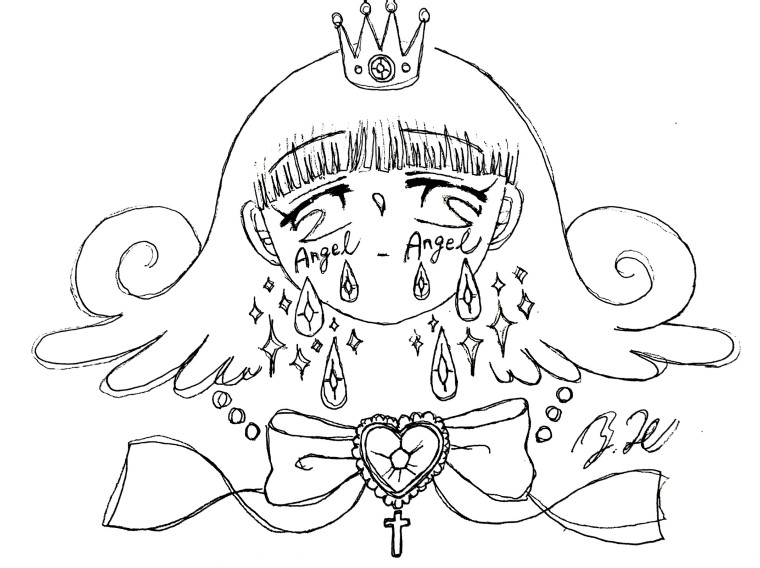
MANAZASHI
このイヤリングの光を眺めていると、あのオモチャの宝石のことをぼんやりと思い出してしまうんです。ニセモノって何だったのでしょうか。ホンモノって何だったのでしょうか。ホンモノと呼ばれるものの放つ光はホンモノで、ニセモノと呼ばれるものの放つ光は果たしてニセモノでしょうか。特別な理想像ばかりがはびこる時代に、私たちのリアルはどんな意味を纏い、どんな風にそれは世界に放たれるでしょうか。
プラスチックの煌めきはそんな問いの上にただきらきらと、ちかちかと降り注ぎます。わたしはその煌めきをどうしようもなく確かなものであると感じます。ああかつての少女の目はそのプラスチックの魔力を歪みなく受け取り、憧れ、手に入れたいと望みました。大人になった彼女には、もうその光は取るに足らないものかもしれません。それでも、なんだか忘れて欲しくないんです、ホンモノと呼ばれる宝石だけがうつくしくて、きちんと証明書のついたものだけが輝いているなんてことがなかった世界で生きていた記憶と、心をときめかせていた記憶を。
そうです、私たちはきっと何者にもなれなくて、きっと何者にも成り損ねてしまう。そんな時代の希望なんて大層な呼び名は望みません。プラスチックのシャンデリアー、ただただ、眩いほどに煌めけ。
―――
第3回
→創作のルーツに向き合うとき